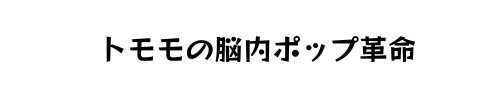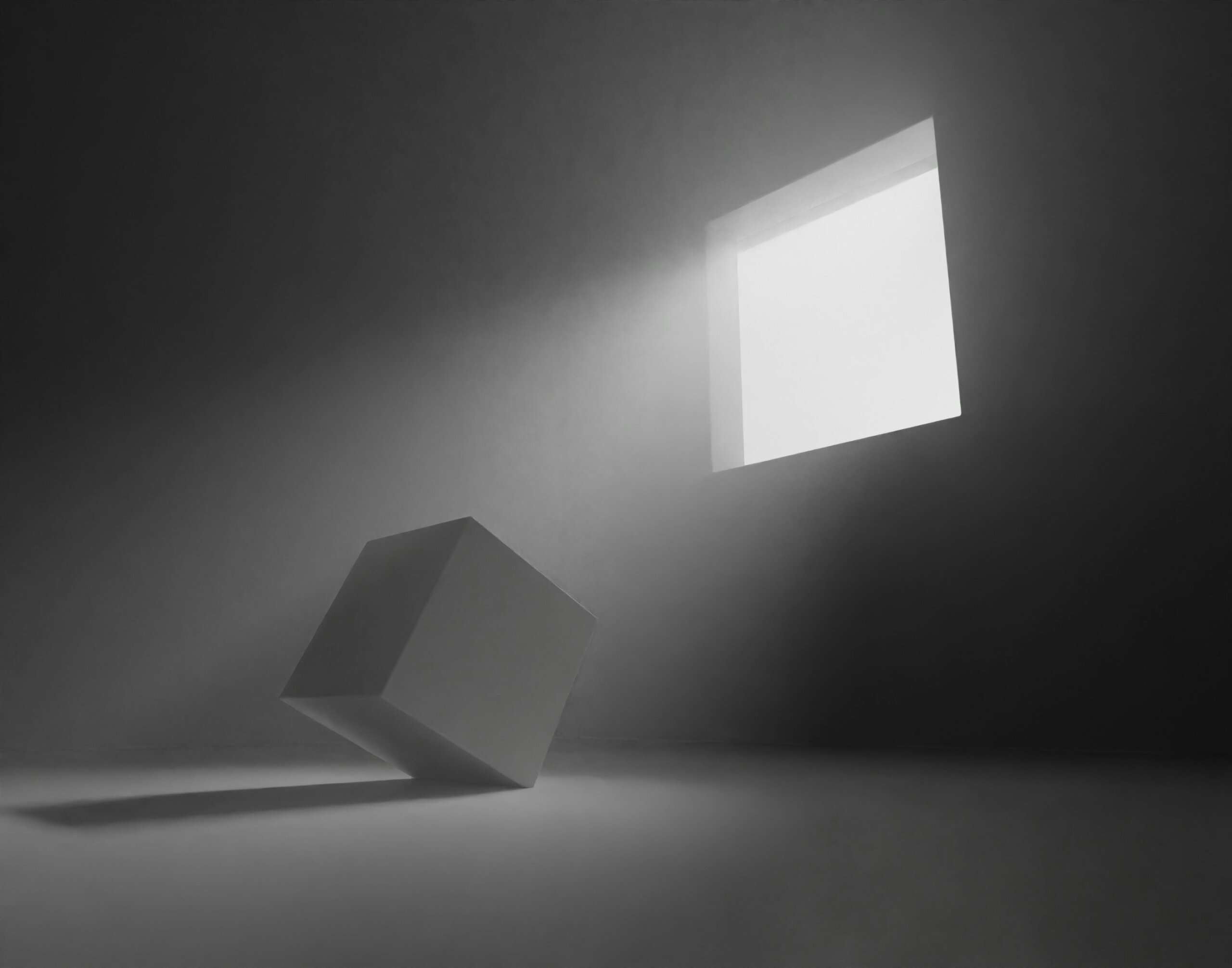ブラインドボックスと、今話題のNFT(非代替性トークン)。
一見、物理とデジタルの全く異なる文化ですが、二つには共通の魅力があるように思うのです。それは「ランダム性」と「希少性」。
この二つを融合させることで、アートトイのコレクション文化を根本から変える、Web3革命が起こるかもしれませんよ・・・
💡 まずは基本から:Web2、Web3、メタバースとは?
【Web2(Web2.0)】現在主流のインターネットです。
Google、X(旧Twitter)、Facebookなどの巨大プラットフォーマーが情報を管理し、
データが中央集権的に集中しているのが特徴です。
【Web3】ブロックチェーン技術を活用した次世代の分散型インターネット。中央管理者が存在せず、データの所有権をユーザー自身が持ち、個人間で直接取引や交流が可能になります。
※ブロックチェーン技術とは、デジタルデータの取引履歴を「ブロック」という単位にまとめ、それを鎖(チェーン)のように連結して保管する技術のことです。
最大の特徴は、特定の管理者を持たず、データをネットワーク上の多数のコンピューターで分散管理することです。
これにより、データは共有され、過去の記録を改ざんすることが極めて困難となり、高い透明性と信頼性が担保されます。仮想通貨やNFTの基盤技術です。
【メタバース】「超越(メタ)」と「宇宙(ユニバース)」を合わせた造語。
インターネット上に構築された3次元の仮想空間を指します。
ユーザーはアバターを通じて参加し、現実世界と同様に交流や経済活動を行うことができます。
NFTはWeb3の象徴的な技術であり、アートトイのような「価値あるコレクション」にこそ、その真価を発揮すると思います。
ではNFT融合がアートトイの世界にもたらす具体的なメリットとはどんなものだと思いますか?
I. NFT融合がアートトイにもたらす「3つの革命」
1. 革命その1:偽物が消える「真正性の証明」
NFTの「非代替性」がコレクションの価値を保証
高額なシークレットフィギュアや限定ソフビがフリマサイトで取引される際、常にコレクターを悩ませるのが「この商品は本物か?」という問題です。現在のメーカーのQRコードによる検証システム(Web2.0的)は有効ですが、NFTはこれをさらに強固にします。
NFT(Non-Fungible Token)の最大の特徴は、「替えが効かないデジタル証明書」である点です。このNFTを物理的なフィギュアに紐づけ、ブロックチェーン上に記録することで、そのフィギュアが「メーカーが製造した本物であること」、そして「現在、誰が所有しているか」が永久に記録されます。
このデータは分散管理されるため、改ざんすることが難しいです。
その結果、二次流通市場から偽物や海賊版を事実上排除することができますし、
高額取引における信頼性が劇的に向上し、不安も解消されます。
2. 革命その2:フィギュアに命を吹き込む「デジタル所有権」
コレクションの価値を「二重化」する拡張性
従来のフィギュアは、現実の棚に飾って楽しむだけの「モノ」でした。
しかしNFTと融合させたら、そのフィギュアは「デジタル空間で使える権利証」も兼ねるようになりますよね。
例えば、フィギュアのNFTを持っていると、メタバースの世界でそのフィギュアをアバターとして使って「活動や体験」もできる。それって面白いですよね。
もっと展開してみるとこんなこともできちゃいます。
- メタバース・アバター化:ラブブやスカルパンダのNFT所有者は、そのキャラクターの3Dアバターとしてメタバース空間で活動できる。(推しキャラに自分がなれるってこと!)
- デジタル・家具/アート:フィギュアのデザインをモチーフにした限定デジタルアートや、メタバースの自分の部屋に飾れる仮想空間用の家具アイテムが付与される。(どんどん想像が広がります!)
- 限定イベント参加権:シークレットNFT所有者限定のデザイナーとのオンライン交流会や、次回作の先行購入権を獲得できたり、さらなるわくわく感を得ることができます。
コミュニティへの帰属意識はさらに強くなりファンたちのつながりも強くなります。
このように、NFTは物理フィギュアの「手触り」を奪うのではありません。
そのIP(知的財産=トイのキャラクターたち)の価値をデジタル空間へ拡張することで、
コレクションの喜びがますます深くなるのです。
3. 革命その3:クリエイターに還元する「自動ロイヤリティ」
持続可能なクリエイター経済圏の構築
現在の転売市場では、フィギュアが発売直後に数倍の価格で取引されても、その利益はすべて転売者に入り、メーカーやデザイナーには一切還元されません。
確かに購入したのは転売者だから・・・とは思う反面、それってデザイナーにとっては不満じゃないかなぁって思うのは私だけでしょうか。
これは、アートトイ文化の健全な発展を阻害しているような気がする・・・
転売ヤーの人は別にそのキャラクターに愛を感じているわけでもなく単に利益目的なのかもしれないからなぁ(モヤモヤ)
でも「NFTの基盤となっているブロックチェーン技術」がスマートコントラクト(自動実行契約)という機能を備えているので、それを使えばこの問題は解決できます。
NFTとして発行される際に、そのデジタルな証明書に「転売されるごとに、売上の〇%を作者に自動で送金する」というプログラムを組み込むことができるので、クリエイターへの継続的な収益還元が可能になる!!!
デザイナーは自分の作品が市場で評価されるほど継続的な収入を得られるようになるからモチベが上がり、結果としてより高品質で革新的なデザインを生み出すことができる!
こうしてアートトイ経済圏全体にポジティブな循環が生まれるのです。
II. POP MARTのIPをNFT化したら?未来のコレクション体験
デジタルガチャ「NFTミステリーボックス」の可能性
NFTの世界ではすでに、デジタルアートやゲームアイテムの「NFTミステリーボックス」という、デジタル版ブラインドボックスが人気ですが、例えばこれをポップマートのIP戦略に当てはめるとどうなるか考えてみました。
- 購入権ガチャ:物理的な人気フィギュア(例:限定版ラブブ)の「先行購入権」を景品としたNFTガチャを販売する。
- 限定デジタルアバター:物理フィギュアの発売に合わせて、その世界観を拡張するNFTアバターコレクションを限定販売する。特に人気シリーズのシークレットデザインは、デジタル上でも超レアアイテムとして高値で取引される可能性があります。
物理とデジタルのハイブリッドが理想的!
物理フィギュアとNFTがセット販売されるハイブリッド型が理想形な気がします。
フィギュアの箱を開ける(物理的な開封体験)と同時に、中のカードのコードをスキャンすることでNFTがウォレット(デジタル財布)に入る(デジタル開封体験)という二重の喜びが味わえるからです。
このシステムであれば、コレクションの「物理的な魅力」と「デジタルの価値・拡張性」を両立できるし、Web3時代におけるアートトイの新しいスタンダードを確立できるのではないでしょうか。
III. 課題と未来:NFTアートトイの普及へのロードマップ
1. 「難しそう」の壁を越えるためのUX(ユーザー体験)設計
NFTやWeb3の概念は、まだ多くのZ世代や一般のコレクターにとって「難しい」「怪しい」といった心理的なハードルがあります。
メタバースやNFTアートトイを普及させようと思ったら、専門知識が不要なUX(ユーザー体験)設計が不可欠だと思われます。
私もこの記事を書くにあたっていろいろと調査する前は、NFTは「怪しい」というイメージを持っていましたし、Web3と言われても「難しくてわからなかった」からです。
とっつきにくいですよね。
そりゃ仮想現実だもの・・・そう思う気持ち、わかります。
でもこんな風に簡単だったら、NFTアートトイの購入者は増えると思います。
ユーザーが「ウォレット(デジタル財布)」を意識することなく、QRコードをスキャンするだけでNFTが自動的に登録される。
複雑な技術を処理するのはあくまで裏方のメーカーの仕事です。
最終的には、NFTという技術の存在を感じさせないほどスムーズな体験ができた!と消費者に思ってもらえることが成功の鍵となると思います。
2. 物理とデジタル(NFT)の理想的な関係
どれだけデジタル技術が進歩しても、フィギュアの「手触り」「素材の質感」「コレクション棚に飾る喜び」といった物理的な魅力はNFTでは代替できません。
NFTはあくまで、物理コレクションの価値を「拡張し」「証明し」「経済的な循環を保証する」ための補完技術であるべきです。
NFTアートトイの未来は、物理とデジタルが互いの弱点を補い合う、理想的な共存関係を築くことで開かれるのではないでしょうか。
まとめ:アートトイは「モノ」から「Web3時代のIP」へ進化する
Web3は単なる一過性のブームではなく、アートトイというIP(知的財産)の価値を最大化し、コレクター、クリエイター、メーカーの三者を結びつける、新しい経済圏の基盤となる可能性を秘めています。
未来のブラインドボックスは、NFTによって「真正性の保証」を、そしてメタバースによって「デジタルな活動領域」を得ることができるかもしれません。
未来のコレクションは、物理的な棚だけでなく、デジタル空間でもきらめいてくれる。
私たちの「推し活」をより愛の深いものに、そして持続可能なものに変えていくでしょう。
関連記事【ダブり・ゴミ問題解決へ】ポップマート人気の裏側にあるコレクターの悩みを解消!の記事はこちら→https://www.bagelya-rokko.online/pop-martーblindbox/