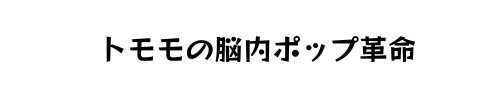【中国発】POP MARTの盲盒(ブラインドボックス)とは?|リサイクルBOXに見る新しいコレクター文化
というタイトルで一本記事を書かせていただいているのですが、ここからさらに考察を深めてみました。
グランピピ、ラブブ、スカルパンダ、クライベイビー… アートトイの魅力にはまっている皆さんは、あの「開封のワクワク」が何物にも代えがたいことを知っていると思います。
YouTubeでも開封動画、とても人気ですよね。
しかし、その「ワクワク」の裏側で常にコレクターの頭を悩ませるのが、
シリーズコンプリートを阻む「ダブり」(重複)と、それに伴う「ゴミ問題」です。
ポップマートのファンコミュニティでは「交換」システムも作動していますが、
Z世代を中心とした若い購買層は、「倫理的な消費」や「持続可能性」を重視する傾向が強いと思うので、この二律背反を解消することが、アートトイ文化がさらに成長するための絶対条件となっています。
今回は、現代のトレンドをふまえた上で、これらの根本的な悩みを解消し、
アートトイ文化をさらに持続可能にするためにはどうすればいいのか、
私なりに考察してみたいと思います。
I. 【現実】進化の芽:大手メーカーが進めるデジタル管理(Web2.0的な基盤)
現在主流のインターネットはGoogle、X、Facebookなどの巨大プラットフォーマーが情報を管理し、ユーザーはそこで交流やコンテンツの消費・投稿をしています。
利便性が高い反面、個人情報やデータが中央集権的に集中しているのが特徴です。
これをWeb2.0とします。
この中でブラインドボックス市場をリードする大手メーカーは、すでにデジタル技術の導入を始めています。
これは、後のWeb3的(応用例でいえばNFTや仮想通貨があげられますが、
その仕組みは中央管理者が存在せず、データの所有権をユーザー自身が持ち、
個人間で直接取引や交流が可能なブロックチェーン技術を活用した
次世代の分散型インターネットです)な進化への重要な布石となっています。
1. 公式導入事例:QRコードとデジタルコレクション
現在、ポップマートなどの大手メーカーは、製品の一部にQRコードやシリアルコードを付与し始めています。
この機能は、単なる購入特典ではなく、以下の二つの役割を果たしています。
- 真正性の証明(偽物対策):パッケージのコードをスキャンし公式サイトで入力する事で、その製品が「正規品であること」を確認できます。この機能があれば偽物取引を牽制することができます。
- デジタルコレクション管理:例えば、SKULLPANDAなどの一部シリーズでは、コードを専用アプリでスキャンすることで、ユーザーのデジタル上のコレクションリストにフィギュアが登録(点灯)されます。
これにより、ユーザーはコレクションの進捗を視覚的に管理できます。
これはまだ物理的な交換システムには至っていませんが、メーカーが初めて物理的なフィギュアをデジタルで一元管理し始めたということがわかります。
2. 偽物・海賊版対策としての「公式化」の限界
デジタル管理による真正性証明は非常に有効ですが、人気シリーズの場合、
パッケージのコードだけをコピーして偽造品に貼ったり、公式アプリの仕様を模倣した偽サイトに誘導する、といった悪質な手口が生まれるリスクもありますよね。
また、メーカーがサービスを終了すれば、デジタルコレクションの記録も消滅するかもしれません。
やはり巨大プラットフォーマーが中央集権的に情報を管理しているインターネットでは限界があると言わざるを得ません。
この限界を超えるには、データの管理・記録を分散させるWeb3技術(NFT/ブロックチェーン)の導入が必要となってくるのではないでしょうか。
II. 【未来への提言】「ダブりゼロ」を実現する究極の進化形
ここからは、現在のデジタル基盤を活用しつつもコレクターが最も望む「ダブりの悩みがない未来」を実現するために具体的にどうすればいいか考えます。
3. 提案①メーカー公式「デジタル・トレーディング・システム」はどう?
最も現実的かつ効果的な解決策は、I章で紹介したデジタルコレクションのデータを活用した、
メーカー主導の「公式交換プラットフォーム」の設立ではないでしょうか。
実現のための具体的フロー
- 登録:ユーザーはダブったフィギュアのQRコードをアプリでスキャンし、
「交換可能リスト」に登録します。 - マッチング:公式交換システムが、登録されたフィギュアと他のユーザーの「欲しいリスト」を自動でマッチング。
- 公式仲介:交換が成立した場合、ユーザーはダブり品をメーカー
(これは認定センターみたいなものでもいい)に郵送し、センターで検品、そして欲しい相手あてに発送します。
これはメーカーとユーザー双方にメリットがあると思う
- ユーザーメリット:フリマアプリのような価格交渉や偽物の心配がなく、公正かつ安全にダブりを解消し、コンプリートを達成できる。
- メーカーメリット:公式サービスを利用させることでブランドロイヤリティを高められるほか、交換データを収集することで市場の「欲しい」情報(在庫データ)を正確に把握できる。
4. 提案②環境とコレクションを両立する「半ブラインド化」はどう?
Z世代が重視する環境問題、特にブラインドボックスのパッケージゴミや不要なフィギュアの廃棄を減らすための、販売手法の進化を考えてみました!
「ガチャ」と「確実性」が両方あってもいいと思う
「ブラインド」のワクワク感を全て排除してしまったら、
それは文化の否定になりかねませんね。
そこで考えたのは「半ブラインド」案です。
- 通常ラインナップの可視化:シリーズの通常版(例えば12種中9種)はパッケージの中身が見えるパッケージで販売します。
確実に欲しい「推しキャラ」だけを安心して購入できたらストレスは減る。(だってお金もかかりますし・・・) - レアリティのブラインド維持:でもそれでは面白くないので、シークレット、スーパーレアといった特定のレア(残り3種+シークレット)だけをブラインド仕様で残すというのはどうでしょう?(賛否両論あると思いますけど)
こうすれば、通常品をダブらせる無駄な出費やゴミを削減しつつ、「激レアを引く興奮」というブラインドボックスの本質的な魅力を維持することができるのではないかぁ。
III. 【新しい消費の形】「所有」から「体験」への価値転換
5. サブスクリプション型「トイボックス」ってあったらいいかも!
洋服のレンタルサービス(例:エアークローゼットなど)の仕組みをアートトイに応用した、「循環型コレクション」はどうでしょうか。
これはコレクターの心理からはほど遠い提案かもしれません。
けれど、流行りだから手にしたいという人も多いし、ブームが去れば捨てられてしまうトイ達もあると思うのです。
それなら循環させるという手もあるかもしれませんよね。
レンタル・買取ハイブリッドモデルがいいんじゃないかな
- サービス内容:月額定額で、ユーザーが登録した「好みのテイスト(ダーク系、キュート系など)」に合わせて、フィギュアが毎月数体届く。
- 返却・循環:飽きたフィギュアは返却ボックスに入れて送り返す。
メーカーはそれをメンテナンスし、次のユーザーに届ける。 - 買取オプション:「これは手放したくない!」というフィギュアは、
レンタル期間に応じて割引された価格で買取できる。
これなら、常に新しいフィギュアを楽しみつつ、モノを溜め込まずに済むというZ世代のニーズに応えられると思います。
また、不要なフィギュアが次の誰かの手に渡ることで、メーカーは廃棄ゼロを目指す循環型ビジネスを構築できます。
6. 「推し活」の多様化:コミュニティ主導の進化
ブラインドボックスの進化は、メーカーだけの問題ではありません。
熱心なファンコミュニティの力も重要だと思います。
- ファン創作と公式ライセンス:デジタル上でフィギュアをカスタムしたり、3Dプリンティング用のデータを作成したりするファンが増加しているとききます。
メーカーが公式にライセンスを付与し、その創作物をWeb3技術で販売・交換できる仕組みを構築すれば、コミュニティからの新しいアイデアが次々に生まれ、IPの寿命が飛躍的に伸びます。 - トイ・シェアリングプラットフォーム:コレクションのコンプリート写真撮影や、一時的なインテリア目的のために、フィギュアを短期間「貸し借り」ができるというファン主導のプラットフォームがあったらいいと思いませんか?
まとめ:未来のコレクター文化は、倫理とテクノロジーが融合した先にあるのかもしれない
ブラインドボックスを今後どう進化させていくか、という問題は、単なる販売手法の変更ではなく、Z世代の新しい価値観(サステナビリティ、透明性)に応える必要性から生まれています。
ポップマートの現在の取り組みは、デジタルによる真正性の管理という、進化の第一歩を踏み出しました。
もしこれに「公式交換システム」という実用的なデジタル機能と、
「サブスクリプション」という循環型ビジネスモデルが加われば、
ブラインドボックスは「環境にも優しく、ダブりのストレスもない、理想的なコレクション文化」へと変貌を遂げると考えました。
未来のコレクターは、より賢く、より倫理的に、そして何より楽しく、
アートトイを愛すること
ができるようになるのではないでしょうか。
LOVE POP!LOVE TOYS!